「受験勉強のストレスで、こどもが不調を訴えており退塾しようか悩んでいる」
「鬱が原因で休塾できるの?」
受験期にストレスで子供が精神的に辛い状態になって体調不良を起こしてしまうことがあります。そんな時どんな対処法があってどういう対応をすればよいのか、親にできるサポートはあるのか。そして、それでも中学受験塾を継続し受験に突き進むのか、それとも休塾をするのか、はたまた退塾を決断するのか。。
この記事では、受験期に様子がおかしくなっていった私の子供への対応や、精神的にまいってしまった友人のお子さまの実体験をもとに、どういう対処をして、その後どうなったのかをご紹介します。
今現在、キツイ厳しい状態で頑張っている子どもをみて、どうしてあげるのが1番いいのか、親はどのように対応すれば良いのか、悩まれている方の参考になれば幸いです。
我が子が鬱かも?チェックポイントは?

受験は多かれ少なかれプレッシャーがかかるため、心が疲れてしまうことがあります。鬱の症状は心だけでなく身体にも現れる可能性があります。
我が子の様子がおかしい、鬱かもと心配なさっている方は、下記のような症状が出ていないか確認してみてください。
- 緊張感や不安が大きくなった
- イライラする、怒りっぽくなった
- 悲しみや絶望を感じている
- 些細なことでひどく傷つく
- 勉強に集中できない、ケアレスミスが増えた
- 成績が急激に下がった
- 食欲がない、吐き気が強い
- 朝起きられない
- 夜眠れない
- 遅刻や欠席が増えた
- テスト本番で体調が悪くなる
- ふさぎこんでしまい、親や友人と距離を置くようになる
まだ10代前半のこどもです。「わたしは受験のストレスで鬱になったんだ」と自分で気づくことはほぼないでしょう。
発熱や鼻水とは違い、目に見える形で症状が出るものばかりではありません。上手く言えない体調不良を抱えながらも、周囲の期待に応えようと人知れず苦しんでいる可能性があります。こどものストレスや鬱を発見するためには、1番の理解者である親が注意して見てあげることが大切です。
万が一、自傷行為を見つけてしまったり死にたいと口にするようになった場合は、さらに要注意です。
こどもの笑顔や表情、口調、目の動きなど、親だから気づけることはたくさんあるはずです。深刻な状態になる前に、しっかりこどもと向き合ってください。

私の子供は、、小5の夏頃に幻聴・幻覚を訴え始めました・・私はすぐさま病院に連れていき、検査を受けさせました。また、私のお友達のお子さんも小5の頃に自分の髪の毛を無意識のうちにむしり取る行動を起こすようになったそうです。
本当に、中学受験は子供にとってとんでもないストレスなのだと親は理解しないといけないと思います。
我が子によくよく気を配り、異変にいち早く気付いてあげないといけないと思いました。
精神的に辛い…親ができるサポートは?

こどもが「中学受験が辛い」と相談してくれた時、親にはどんなことができるでしょうか。親ができる、親だからこそできるサポートをまとめました。
- 睡眠時間を確保する
- 栄養バランスの整った食事を作る(食欲に合わせて)
- こどもが好きなメニューを多く出してあげる
- こどもの話をたくさん聞く
- 勉強を忘れられるような場所へ出かける
- 会話で、勉強や受験などのワードを避ける
勉強に集中していなかったり、成績が落ちていると親は気が気でないでしょう。
塾を辞めたい、受験を辞めたいと言われた時に、「ここまで時間とお金を費やしてきたのに」「そんな安易に辞めていいのだろうか」と考えてしまいがちです。
しかし、ここで「勉強しなさい」や「やめてどうするの?」という言葉は禁句です。
精神的に辛くなってしまった場合は、まず健康的な生活を意識してあげてください。
1日3食の食事や早寝早起きを心がけましょう。夜寝られない場合でも、起きて作業したり、明るい部屋にいるのはなるべく避けてください。横になるだけでも身体は休められています。
食欲がない時は消化の良いものを中心に出したり、こどもが大好きなメニューを出してあげたりすると、気持ちが落ち着きやすくなります。
一旦受験のことや勉強を忘れて大笑いしたり、時間を忘れて遊べるような場所へでかけるのもおすすめです。
実際に、「もしここで塾をやめて受験をやめるとなったら、なんてダメな人間なんだろう」と自分を卑下してしまう子は多くいます。そんな子は、期待に応えられないなら要らないと言われてしまうのではないかと、日々ビクビクしています。
中学受験をしようがしまいが、大事なこどもであることには変わりない、ということをこども自身が肌で実感できるような温かい言葉をたくさんかけてあげてください。

私の場合はまず小児科に連れていきました。そこから総合病院にある子ども専用の心療内科を紹介していただきました。。そこであらゆる検査をして、、そして毎月1回心療内科に通うことになりました。
お医者様からは「塾はやめたほうがいい」とはっきり言われたのにも関わらず、塾をお休みする形をとりました。。辞めよう、とは言えませんでした。(申し訳なかった、、)そして小5の夏は家族旅行をしたり、実家のおじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行かせたり、勉強はなにもせず楽しく遊びまわりました。
ちなみに、髪を抜いてしまうお友達のお子さまは、親子で話し合った末に潔く塾を辞めました。
退塾し受験を断念するか、そのまま続行か?

こどもの体調を最優先するのは大前提ですが、中学受験そのものを諦めるのはもったいないと言えます。受験のストレスと言っても原因によっては、工夫や何かを変えることで解決する場合があるからです。
受験の鬱は3つの型に分類され、「勉強に集中できず成績が落ちた」という同じ結果でも、そこに至る原因となったストレスには様々なことが考えられます。
- プレッシャー型
- 親や周囲の期待が大きすぎる
- 自分が希望していない学校への入学を期待されている
- モチベーション喪失型
- 塾が合わない
- 塾での人間関係に悩んでいる
- 授業の内容についていけない
- 自宅だと親がうるさく口出しをするので集中できない
- 比較・競争型
- 友人と比較されるのが苦しい
- 塾に成績が貼り出される
これは受験ストレスの一例です。勉強に集中できずに成績が落ちるのはこども本人の問題だけでなく、様々な要因が絡んでいることがわかります。
「受験がストレス=受験をやめよう」と短絡的に結びつける前に、立ち止まって考えてみてください。
もしかしたら、こども本人は勉強が大好きで行きたい学校があるけれど、単に塾が合わなくて辛いだけかもしれません。また、本当は別に行きたい学校があるのに、周囲や親の期待が大きすぎて声をあげられずにずっと悩んでいる可能性もあります。
もちろん、心だけでなく身体にも不調が現れてしまい、受験を断念せざるを得ない場合もあるでしょう。そんな場合でも「せっかくここまで頑張ってきたのに」と言いたくなる気持ちを抑えて、回復するまで見守ってあげてください。
退塾したからといってそこで受験への道が絶たれるわけではありません。他の塾への転塾や自宅学習もできます。退塾して心身ともに元気になった時に、やはり受験に向けて一生懸命頑張ろうと思えるかもしれません。
退塾したからもう中学受験はおしまい、続行するなら絶対に受験、と決めつけるのはやめませんか。転塾や休塾、志望校の変更、一旦全ておやすみして考えてみる、様々な選択を考慮してみましょう。

うちの子の場合はプレッシャー型だったと思います。自分で自分を追い詰めるのです。もちろんそこには、私たち親の何気ない言葉に反応していることも大きいです。
ちょっとした親の会話を聞いていて、(勝手に)プレッシャーを受けていたのだと思います。
「ママは私に塾に行ってほしいんでしょう??(涙)」と言って涙を流す子供を見て、酷い情けない親だと自分でも思うのですが、、大丈夫なんじゃないか?頑張れるんじゃないか?と思ってしまい、「辞めていいよ」とは言わなかった。「自分で決めたらいいよ。辞めても続けてもどっちでもいいよ」と子供に責任をふってしまった、、、本当にダメな親です、私。
医師には「子どもに決めさせるなんてなんて酷いことを。子どもは親の期待に応えようと頑張るのですよ。親が言ってあげないでどうするんですか」と言われました。
塾の休塾の制度を利用する

実際の休塾制度について確認してみましょう。実は、多くの進学塾には休塾制度がないのです。つまり、休塾したい場合は一旦退塾の手続きを取ることになります。
塾側には休塾にメリットが少ないからだと考えられます。休塾期間の授業料は入ってきません。また、塾では受け入れできる生徒数が決まっています。休塾制度を利用して休んでいる生徒がいる場合には、新たな生徒を入れることができないのです。
塾としては、授業料を払ってくれるなら休んでもいいよというスタンスなのかもしれません。
数は少ないですが、休塾制度の記載がある塾における休塾の期間、料金などを紹介します。
- 進学塾ヴィスト(千葉)→原則6ヶ月以内、休塾料金なし
- 類塾(大阪・奈良)→最長3ヶ月、休塾料金は月額2,000円(税込)
- 湘南ゼミナール(東京:神奈川、2019年の記載)→原則3ヶ月以内、休塾料金なし
また、進学塾大手の日能研に関しては休塾の手続きができるという口コミはありましたが、実際に日能研のホームページには休塾に関する記載は見当たりませんでした。他、四谷大塚、早稲田アカデミー、サピックスなどの大手進学塾では休塾の制度はないため、一旦退塾することになるようです。

うちの場合は、退塾の前に休塾はできないか確認してみました。ちなみに塾はサピックスです。
サピックスの制度にはないのかもしれませんが、その当時、塾長は休むことを認めてくださいました。確か、夏期講習の間だったら休塾してもいい、でもそれ以上長くなるといったん退塾してまた入塾テストを受けてください。と言われたように記憶しています。(休塾中の塾代については忘れてしまいました、、ごめんなさい。)
また、ストレスで体調不良を訴えるお子さんは時々いらっしゃる、ということもお話くださったと思います。
今、お子さんのことで悩まれている方は、すぐにでも直接お世話になっている塾に相談してみることをおすすめします。そして休塾について、また退塾について聞いてみてください。特別な措置をとっていただけるかもしれません。
まとめ

成績が伸びずに塞ぎ込んでいる、笑顔が少なくなった、やる気を感じないといった心の不調だけでなく、食事を摂ると吐いてしまう、夜眠れない、という身体の不調が現れた場合は注意が必要です。
ストレスの原因を取り除き、しっかり休養することが大切です。周囲の期待に応えようと頑張りすぎる子は、「辞めたい」「休みたい」と口に出せないことがあります。
受験のストレスで鬱っぽくなったからといって勝手に退塾させてしまうと、「期待に応えられなかった」とさらに落ち込ませることも考えられます。
ストレスでまいっている時は、焦って何かを決断することは避けましょう。
退塾はいつでもできます。塾に休塾制度がなかったとしても、休むことはできます。
こどもの体調やちょっとした変化をしっかり観察して、ストレスや鬱の原因を取り除き、今後の進路に対しても柔軟に対応してあげるようにしましょう。

最後に、うちの子どもの話ですが、、
結局、小5の夏期講習の間だけ休塾し、9月からは塾に戻りました。夏休みは大いに遊んで、テキストはいっさいみませんでした。
後になって子どもとも話すのですが、「あの休みがなかったら私は潰れていた」と言っていますね。。そして「9月から塾に戻るのは実は物凄く嫌だった。ママが行ってほしいだろうなと思ったから仕方なく行った、、」と。「でも、今は(中高一貫校に入学して卒業して)本当に良かったと思う」と話しています。
うちの子は結果オーライでしたが、その当時は相当悩みましたし、塾に戻ったからといってしっかり勉強ができるような状態でもなく、泣いて泣いて何も手に付かない状況が続きましたので、志望校も下げざるおえませんでした。だから何が正解かはわかりません。
ただお子さんの様子をよく見て、とにかくできる限りのケアを、サポートをしてあげてほしいと思います。心が壊れてしまってからでは遅いので、慎重なご対応をお願いします。また専門家の医師に見ていただくことはとても大切だと思います。

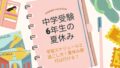

コメント